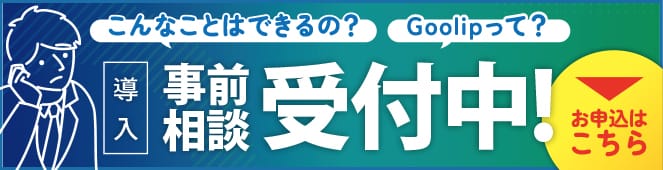建設業許可のキーパーソンとは?

建設業許可のキーパーソンとは?専任技術者と経営業務管理責任者の要件を図解で解説
建設業を始めるには、国や都道府県から「建設業許可」を取得する必要があります。その許可取得において、特に重要な役割を担うのが「専任技術者」と「経営業務管理責任者(通称:経管)」です。
令和5年の建設業法改正により、これらの要件が一部緩和され、より多様な人材が建設業界で活躍できる道が開かれました。本記事では、設計業務経験者が専任技術者になれる可能性と、経管の要件緩和について、図表を交えてわかりやすく解説します。
専任技術者の役割とは?
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」の配置が義務付けられています。専任技術者は、施工管理、安全管理、技術指導など、工事の技術的責任を担う重要な役割を果たします。これまでは、施工管理技士や建築士などの国家資格を持つ者が主な対象でした。
実務経験による認定の道
令和5年7月の建設業法改正により、専任技術者の要件が緩和されました。これにより、資格を持たない者でも、一定の実務経験があれば専任技術者として認定される可能性が広がっています。
特に注目すべきは、設計業務に従事してきた技術者の扱いです。設計業務が建設工事に密接に関わる内容であれば、施工現場の経験がなくても、実務経験として認められるケースがあります。
専任技術者は、営業所において以下のような技術的業務を担います。
| 業務区分 | 内容 |
|---|---|
| 契約管理 | 技術的な契約内容の確認、履行の監督 |
| 技術指導 | 作業者への技術的な助言・教育 |
| 安全管理 | 現場の安全対策の立案・実施 |
| 発注者対応 | 技術的な説明や調整、報告業務 |
営業所に常勤し、施工現場とは異なる立場で技術的責任を果たすため、専門知識と実務経験が求められます。
専任技術者になるための要件
従来の要件は以下の通りです。
| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 学歴+経験 | 高卒+5年、大卒+3年の実務経験 |
| 国家資格 | 施工管理技士、建築士など |
| 実務経験のみ | 資格なしの場合は10年以上の実務経験 |
このように、資格または長期の実務経験が必要とされていました。しかし、令和5年7月1日の法改正により、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、検定合格後の実務経験年数が短縮されるなど、要件が緩和されました 。
※技術検定合格者の扱い
| 技術検定 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 1級検定合格者 | 3年以上 |
| 2級検定合格者 | 5年以上 |
これにより、検定合格者は学歴に関係なく、短縮された実務経験で専任技術者になれるようになりました。
URL:国土交通省 技術検定試験について
設計業務は実務経験として認められるか?
認められる可能性は十分にあります。建設業許可事務ガイドラインでは、設計業務が「建設工事に関する技術的管理に資する業務」である場合、実務経験として認定されると明記されています。
ただし、以下の条件を満たす必要があります:
- 設計業務が建設工事に関連していること(例:建築設計、構造設計など)
- 実務経験が10年以上あること(資格なしの場合)
- 経験内容を証明する書類が提出できること
設計業務が施工に直結する内容であれば、現場経験がなくても「技術的管理に資する業務」として認定される可能性が高くなります。
証明書類の例
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 業務契約書 | 設計業務の内容と期間の確認 |
| 所属企業の証明書 | 在籍期間と職務内容の証明 |
| 請求書・納品書 | 実務の実態を示す資料 |
設計業務が施工に直結する内容であれば、現場経験がなくても認定される可能性が高くなります。
専任技術者の配置と兼務の可否
専任技術者は原則として営業所に常勤し、他の職務との兼務は制限されます。ただし、以下のような例外もあります。
〇 同一営業所内での兼務 ⇒ 技術者が複数業種を担当する場合は可
〇 他営業所との兼務 ⇒ 原則不可
〇 現場との兼務 ⇒ 営業所と現場が近接し、常時連絡可能な
体制がある場合に限り可
経営業務管理責任者とは?
経管は、建設業の経営に関する業務を統括する責任者です。主たる営業所に常勤し、財務管理、労務管理、運営業務など、企業運営の根幹に関わる業務を担います。具体的には、資金繰りや契約締結、従業員の管理、経営方針の策定など、経営判断に関わる業務全般が対象となります。
経管の主な業務
| 業務区分 | 内容 |
|---|---|
| 財務管理 | 資金調達、資金繰り、支払い管理 |
| 労務管理 | 勤怠管理、社会保険手続き、給与計算 |
| 運営業務 | 経営方針の策定、契約締結、組織運営 |
従来の経管要件
| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 法人 | 建設業で5年以上の役員経験 |
| 個人 | 本人または支配人が5年以上の経営経験 |
| 補佐経験 | 準ずる地位(事業部長など)で6年以上 |
従来、経管として認定されるためには、法人の場合は「建設業における5年以上の役員経験」、個人事業主の場合は「本人または支配人が5年以上の経営経験」が必要でした。また、役員ではない場合でも、事業部長などの準ずる地位で6年以上の補佐経験があれば認定されるケースもありました。
このように、建設業における実績と責任ある立場での経験が重視されていたのです。
補佐制度の導入(令和3年改正)
令和3年の改正では、経管の認定要件が大きく見直されました。特に注目すべきは、「補佐する者」の制度の導入です。これは、常勤役員に経営経験が不足していても、補佐する者がいれば経管として認定されるという新しい仕組みです。
補佐する者の要件
- 財務管理、労務管理、運営業務のいずれかまたはすべての経験が5年以上
- 経験は重複していても可(例:同時期に3業務を担当)
補佐者の構成例
| 構成 | 内容 |
|---|---|
| 単独 | 1人で全業務を担当(3業務×5年) |
| 分担 | 複数人で分担(例:財務担当、労務担当、運営担当) |
常勤役員の要件(令和5年改正)
補佐制度を活用する場合でも、常勤役員には一定の経験が求められます。令和5年の改正では、以下のいずれかの要件を満たすことが必要とされました。
① 要件A 建設業で2年以上の役員経験+5年以上の管理職経験
② 要件B 建設業で5年以上の役員経験
このように、補佐制度を活用する場合でも、役員自身が一定の業界経験を持っていることが前提となります。これは、経管としての責任を果たすために最低限の業界理解が必要であるという考え方に基づいています。
証明書類の例
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 登記簿謄本 | 役員としての在籍確認 |
| 確定申告書 | 個人事業主の経営実績証明 |
| 組織図・業務分掌規程 | 補佐者の業務内容の確認 |
| 工事契約書・請求書 | 実務経験の裏付け |
注意点
- 他社との兼務は不可(専任性が求められる)
- 名義貸しは厳禁
- 書類不備は認定不可の可能性あり
まとめ
建設業許可の取得には、「専任技術者」と「経営業務管理責任者(経管)」の配置が不可欠です。令和の法改正により、両者の要件が緩和され、資格や経験の幅が広がりました。これにより、設計業務経験者や管理職経験者など、従来は対象外だった人材も建設業界で活躍できる可能性が高まりました。人材確保が課題となる中、制度の柔軟化は業界の持続的な発展に寄与する重要な一歩と言えるでしょう。
【関連記事】
【国土交通省 資料】